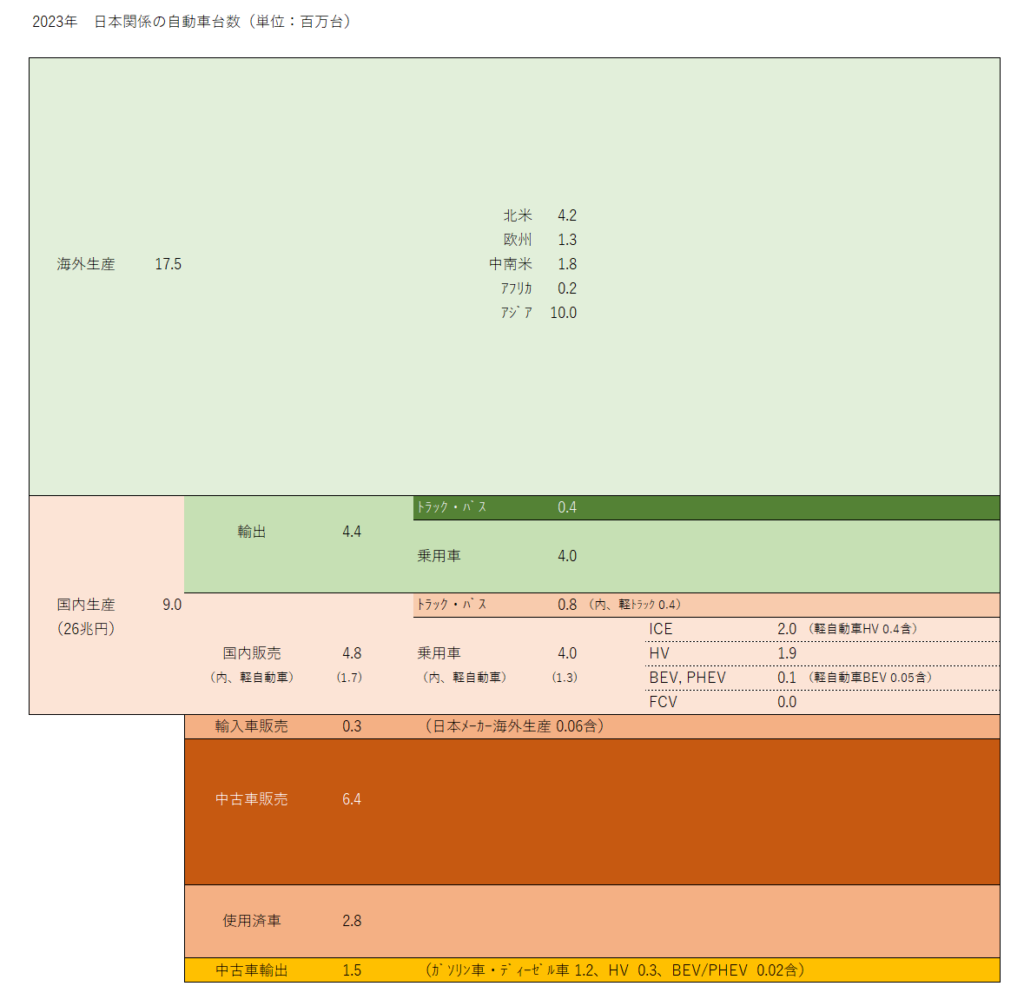マーフィーの法則
いろいろなあるあるの中でも、私には、マーフィーの法則が車関係で発動することが多い。毎日の通勤に往復1時間強を車中で過ごす私にとっては、一日のうちの4%相当を車とともに過ごしていることになる。あまり変化のない仕事、睡眠、食事の時間を除くと、一日のうちの4%は小さくない比率だ。だから、車に関する法則発動が多くても不思議ではないのかもしれない。
洗車をすると雨が降るのは、よくきく法則だ。また、自分自身としてもその経験は少なくない。ただし、毎日雨が降ってもおかしくない東南アジアにいると、これが法則とは言えないことも実は知っている。
東南アジアの環境を除いてもあるあるなのは、同時に複数台の車が交差点で出会うこと。もちろん、無条件というわけではなく、前後5分以上の間にすれ違う対向車さえないのに、自分の車が交差点に接近する際に(信号のない交差点で、自分が走行中の道路が優先であっても相手側がそうであっても)に、突然、ほかの方向からも同時に車が接近するようなケースのこと。結構な頻度でこれに出会う。
それぞれ別方向から交差点へアプローチする車が、別の車が近づいていることで、それぞれが我先にと交差点に入ろうとスピードを上げる結果、同時に交差点に接近する結果に至っているのかもしれない。ちょっと仮説をいくつか考えてみたい。意味ないけど。